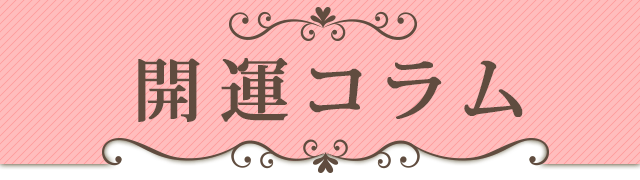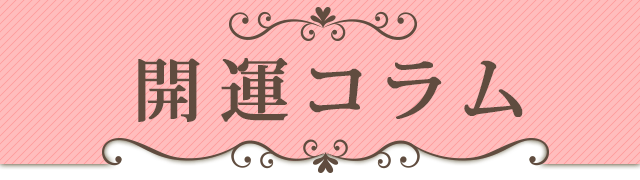「誕生木」があります。誕生石、誕生色のように、特定の月に親しむと、運気に弾みがつく「ラッキー樹木」が選ばれていますよ。
10月は「栗」です。でも、なぜ、10月の誕生木に選ばれたのでしょう。
今回は、栗について、スピリチュアルな観点も含め、いろいろお教えいたします。
実りの秋
10月は「実りの秋」の季節到来です。
この「実り」を象徴する樹木として、栗が10月の誕生木に選定されました。
でも、実をつける樹木は、栗のほかにもいろいろあります。なぜ、栗だったのでしょう。
これは、日本の歴史に関係があります。
今から五千年以上前の縄文時代、人々の命を支えていたのが栗でした。
縄文時代を代表する青森県の三内丸山遺跡では、栗の遺物が大量に出土しています。縄文人は栗を栽培し、栗が集落の食料基盤となっていたのです。栗は高カロリーで栄養価も高く、人々の命を支えるのには最適な食材でした。
三内丸山遺跡のシンボルタワーとなっているのが、巨大な6本柱です。この柱も栗の木ですよ。
栗は食料としてだけでなく、建材、燃料など、縄文人の生活全般を支えていたのです。
栗がなかったら、縄文人の多くは餓死していたかもしれません。そして、その結果、子孫である私たちも、ここにいなかったかも……。
なので、日本人にとって、栗は大きな意味を持った存在。
実りの秋を象徴する樹木に、私たちの先祖の命を支えてきた栗が選定されるのは当然なのです。
縁起の良い栗
縄文時代の祭祀用の建物には、栗の大木が使用されていました。縄文人は、生活を支えてくれる栗を「神様からの贈り物」と考え、神様のそばに、栗の木を置いたといわれています。
この縄文人の思想は、日本で廃れることなく、栗を食べて厄除けをしたり、縁起を担いだりするなどの風習を生み出しました。栗の木は成長して実をつけるまでに長い年月がかかるため、不老長寿の象徴ともされてきましたよ。
戦国時代の武将は、栗を食べると、元気になるだけでなく、戦いで勝利をおさめられると、栗を愛好していたのは、よく知られています。
お正月に「栗きんとん」を食べるのも、縄文由来の栗信仰の名残です。黄金色に輝く栗の実は小判を連想させることから、金運上昇、そして、今年一年の繁栄を願う縁起物とされてきました。
このように栗は、勝負運・金運を高め、長寿をもたらす縁起物とされ、日本人の生活に深く根ざしてきたのです。
栗に親しみましょう
秋の風情を楽しみながら、野山の栗を持ち帰れる「栗拾いツアー」などのイベントが各地で開催されています。そこに参加してみるのもオススメです。
お店で売られている栗は、イガの部分が取り除かれて実だけですね。昔の人は、イガの部分に「魔除け」の効果があると信じていました。
野山に出かけると、イガの部分も目にしながら、栗の実を拾える利点があります。
「繰り」と「栗」の「くり」の同じ音に縁起を担ぎ、栗の木を1年使うと「繰り回し(金銭などを、都合をつけてやりくりすること)」が良くなるといわれてきました。
ここでオススメなのは、栗材の八角箸です。八角箸は縁起良い形とされ、持ちやすいだけでなく、「末広がり」の縁起物としても使われています。
「秋の実り」の時期に入手した栗の八角箸に親しむと、金運・財運が高まるかもしれませんよ。
以上のことを参考に、10月生まれの人はもとより、他月生まれの人も、「実りの秋」の時期に、栗の縁起にあやかってみるのはどうでしょうか。